|
「……決意……それが、武器のこと?」 「そう、武器です」 梶原邸の夕餉前、復活したを無言で手招きしたはこそこそと庭木の茂みの裏で打ち明けた。 「実際にこちらの世界の戦闘に出て痛感しました。……武器が必要です。すくなくとも、わたしには……。さんやさんほど戦えないにしても、せめて訓練ははじめるべきだと」 先代の白龍の神子たるには特定の武器がない。彼女の世界における怨霊との戦いは、主に霊力や神通力での仁義なきどつきあいである。お札などの道具を使うことはあっても、実際に武器を手に攻撃する必要性はうすかった。 は生真面目に眉根を寄せる。 「なんて言ったらいいか……とにかく、こちらの世界の怨霊はエネルギッシュです。数も多い」 「……龍神の加護が欠けているから」 「そうなんです。そのぶん神子にもエネルギッシュさが求められるようです。今のわたしにはさんのようなエネルギッシュさがありません。このままじゃ足手まといになってしまう。王族として軍を率いているさんにはその心配はありませんが……」 あくまでもはシリアスである。シリアスにおのれの戦力を考察している。 は首をかしげた。 本日ためしてみたところ、とでもこの世界の怨霊を浄化できることがわかっている。さらには、九郎ら八葉との協力攻撃においても白龍の神子ポジションにつけることが判明している。 要するに、浄化・術限定とはいえ一時的にの代理がきくということになるのだ。 にとっては不思議なことに、それでもは無力を嘆く。 「なぜ? わたしたちはこの世界の神子じゃない。この世界の戦力になろうと実力以上にがんばりすぎる筋合いはない。必要もない」 「うっ……そ、それは、そうなんですけど」 「それに、このうえ神子として役立つところをみんなに見せるとにおこられる気がする……」 「そ……それも、確かにそうなんですが」 実は、すでにはに武器取得案を却下されていた。 『……。はもうじゅうぶんの戦力になれるわ。それ以上の戦闘能力を欲するのはではなくて源氏よ。忘れてはいけないわ、私たちはのためにここにいる。そしては、武器を持ったことのないあなたが今から特訓という苦痛とひきかえに物理的攻撃力を得ることを決して望まない。 ……まあ、そうね、仮にそれが唐突に目覚めたあなたの趣味だとしても。実戦のレベルは容易ではないわよ。は性格がやさしいから、どう贔屓目に見ても向いていないと思うわ。私はおすすめしない』 亡国の王女、あくまでも微笑みながらの長台詞であった。 うんうん、と隣のもしきりにうなずいていた。 『ちゃんたちは無理に危ないことしないでいいよ! ホントは戦場につれてっちゃうのも危ないんだけど……でも、本陣の奥で待っててくれるなら、すごくうれしい。……あのね、ホントに戦わなくてもいいんだよ。だってちゃんは自分の世界でちゃんと戦い終えたんだから、もういいんだよ。これはあたしの戦いだから。あたし、子どものころからチャンバラごっこ得意だったし……』 譲くんとか近所の男の子には負けたことないし、将臣くんとは一進一退のドローだったもん。 力強く親指を立てるは、確かにこのサバイバルな世界の神子にふさわしかった。 とて、彼女たちのいわんとするところはわかる。そのとおりだと思う。 しかし。 「絶対に本陣が安全だという保障もありません。みなさんは可能なかぎり守ると言ってくれますが、そういうわけにもいかない状況もあるでしょう。――わたしだって人間相手に戦いたくはない。だけど、いざというときに何一つ役に立たないのはもっとごめんです。……自分の身を守るためにも、万が一のときにためにも。なんらかの対策は必要のはずです」 やわらかい色の瞳が、はっきりと意思をたたえる。 はふと小さく笑った。そう、おそらく神子の中でもっとも御しやすいと思われているだろうだが、その実やさしくて流されるだけの人ではない。こうと決めたら頑固なのだ、とても。心から納得しないかぎり、誰になんと言われてもあきらめないのだから。 とりあえずとのタッグに反対されながらも、めげずにに相談してくる程度にはまったくあきらめていないのだ。 先々代の白龍の神子は、ひょいと手近にころがっていた木の枝をひろった。 膝をかかえてしゃがみこみ、おもむろにガリガリと地面に絵を描きはじめる。 「……つまり、あつかいがむずかしくなくて、ある程度以上の攻撃力があり、なによりも持ってるだけで敵の戦意をそぐような武器」 「え……?」 「そういうのをの龍につくってもらったらいい」 さん……! てっきり、いつもの淡々とした口調でずばりと反対されると懸念していたは、思いがけない展開にぱっと顔をかがやかせた。 はにかみながら嬉しそうに差し向かいにしゃがみ、わくわくと木の枝が描き出すものを見つめ――しだいに困ったように眉尻を下げた。 「さん……こ、これ……?」 「うん。これ」 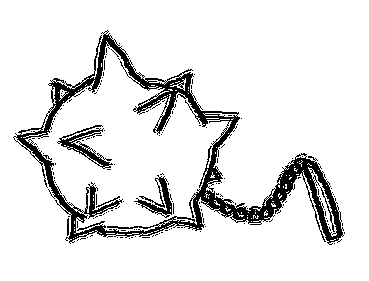 「………………」 「おおきいほうがいい。だいたいの身長くらい。」 「……し、しんちょ」 「神子しか使えない武器だから、きっと龍神なら反則的に軽くしてくれる。……そうだ、この鎖はこれより長いほうがいいかも。それに、この鉄球はもっとトゲトゲしててもいい」 「鉄球!? 鉄球なんですかこれ!?」 「鉄球っぽい何かでもいい。ともかくこれを持ち上げたら敵はまず寄ってこない。振り回そうものならふつう逃げる。もしも逃げない敵がいたとしてもちょっと当てさえすれば一撃でカタがつく。特別に技を知らなくても立派に身を守れる」 「そ、それは……っ」 なにからつっこんでいいかわからないといった風情の真っ青なに、はふだんどおりの顔で率直に尋ねた。 「――武器がほしかったのではないの? きみが使える武器」 その問いの意味するところを察して、は息をのんだ。 はっと顔をあげ、しずかに瞬く双眸を見る。 (きみのための武器だよ。どんなふうに使うかは、きみが決める。つくるもつくらないも、使うも使わないも。……そんなにこわいなら、やめたらいい) 神子同士のホットライン。 のほそい声がの頭に直接ひびく。 ただ、と声は言う。 (……きみ、工夫するのは得意だとばかり思ってた) それは、ひどく挑発的に。 今度こそは絶句し、目を丸くした。の表情は変わらない。深い色の瞳だけが、きらりと艶やかに光をはじく。 先々代の白龍の神子はそれ以上なにも言わず、木の枝を地面に置いて腰を上げた。 そのまま立ち去ろうとする背中を、先代の神子は引きとめようとして――ためらったのち、まったく違うことを告げた。 「……ありがとう、さん」 べつに、と予想通りにはつぶやき。 はその場にしゃがみこんだまま、地面に描かれた珍妙な武器の図をひたすらに凝視し、それはもう足がしびれて悶絶するまで一心に悩みつづけたたのだった。 「……それで、この…こんな有様に?」 縁台に立ち尽くすの声はめずらしく頼りなげだった。 「うん。結果的に」 まったく遠慮なくうなずく。 前回返還時同様、現場はまたしても早朝の梶原邸。 事件の犯人は――結局、寝室に戻ることのなかった先代の神子。 そう、苦悩のすえはおのれの武器を白龍に願い、みごと授与されるに至ったのだ。 カッと鮮烈な光とともに空中に出現し、庭に着地したそれは、の予想通りの姿かたちをしていた。いつも遠慮がちな神子にいつになく頼られて、ついはりきってしまった白龍の意気込みがうかがえるというものである。 しかし、そのとんでもない、思いもよらない光景に、庭先にとおりかかった者は皆ひとり残らず、唖然として足を止めた。冷静沈着なや弁慶とて例外ではない。やはり炊事場から駆けつけた譲はしゃもじを取り落とし、景時は 「…あれも式神かな?」 と素でボケた。 もっとも立ち直りが迅速だったのは、常日頃からボーダーレスにおおらかな感性をたたえる当代白龍の神子だった。 「うわー、うわー、いいないいなー! ねえちゃん、もういっかい持ってみて」 「あの、わたしにとっては見た目よりずっと軽いんですよ。簡単に持ち上がるんです」 「それがスゴイよ! 鉄のふりしといて憎すぎるよ! いやあ、工夫されてるなあ。ちゃんの白龍もいい仕事してるー」 「……本当に、アイディアをくれたさんと白龍のおかげですね」 世にもまれな鉄球を軽々持ち上げたがさわやかにコメントし、またまた謙遜しちゃってえ、と朗らかにがからかう。 それは直径およそ神子の身長ほどの、巨大な鉄の球体だった。 いたるところに大きな円錐型のトゲが突き出し、攻撃力および視覚的なおそろしさを倍加させている。おそらく球体に接続された長い鉄鎖と、鉄鎖につづく柄でもって、持ち上げる・投げる・振り回すなどのアクションが可能となる武器。 「そう……の入れ知恵なのね」 「……入れ知恵っていうか」 「でも入れ知恵なんでしょう」 「相談されたから提案はした。一晩中ずっと悩んで決めたのは。応えたのはの白龍」 「…………」 金色の睫毛にふちどられた双眸が、なぜ、と鋭くたずねる。 戦わずとも済んだ彼女になぜ今さら武器を持たせるようなまねをする? そらさずに、深い色の瞳が見つめ返した。 「そんなふうに……が心配して怒るってことも、は知ってた。や八葉が守ってくれることも。……それでも、万が一のときがあるはずだって言う。一人だけ戦うすべを持たないまま、そのときを迎えるのはいやだって」 「そんなこと……それは、怠惰ではないわ」 「うん。ていうかあれだけゴッツイ術が使えておいて無力扱いされても……って言ったんだけど、の中ではそのくらいはふつーの域を出ないみたいだった」 「…………」 さきほどとはまた違った心境でものかなしげにを見つめる。 謙虚も徹底すれば武器となる。のためにあるような言葉である。 誰が否定しても本人は 『まだまだ未熟者』 と心から思っている。いいかえれば、わりあい常に向上心にみちあふれ――時と場合によっては、鉄球を武器とすることも辞さない跳躍した覚悟をも獲得することになる。 はのそのあたりの不治の病的な傾向を察していた。 ゆえに、こりゃあ何言ってもダメだなと判断したのち、逆に背中を押す方針をとったのである。 「……なぜそこで背中を押すの」 「せめて堅実なルートを指し示してみようかと」 「あなたの 『堅実』 に関しては少し話し合う必要がありそうね」 ふたりの視線の先には、問題の鉄球をかこみ、わいわいとににぎやかな皆の姿がある。 早朝鍛錬から帰参した九郎やリズヴァーンも加わり、ひたすら驚き感心する者、おそるおそるつつく者、真顔で分析する者、持ち上げようとして挫折する者などなど、彼らの反応はさまざまだった。ただし、少なくとも今のところ頭ごなしに否定する人間はいない。 ふだんになく憮然とするに、ふだんになくクスッとは笑った。 だいじょうぶ、と。 「いざというときは、わたしも出る」 ――こうして、先代白龍の神子は武器を神に願い、鉄球を手に入れることとなった。 外見上は鉄、重量上は発泡スチロール、感触上は低反発クッション、かつ打撃付加効果100%気絶および物理的攻撃力皆無という、武器としてはきわめて異色なそれは、こののち、案の定これを目にした何も知らない敵を心底びびらせることとなる。 ちなみに、白龍の神子の中で唯一特有の武器を持たない先々代は、この先もなお武器を願うことはなく、彼女の戦闘能力については――現在、ただ白龍の神子たちだけが地味に知るばかりである。 |


確か、モーニング・スターという名前の武器だった気がいたします。
その名前のムダなさわやかさが持ち主に似て (…いると言ってもいいものかどうか)
(はちみつ印。管理人ゆの:2009.02.14)